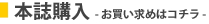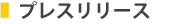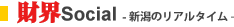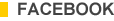併願受験考・国公立大学編
2025年05月27日
一般選抜で大学入試に挑もうとする場合、併願受験はまず避けられない。にもかかわらず、併願を考え始めるとカネ(受験費用)、不安(自信喪失、周囲のデキが気になる)、焦り(併願を増やすべきか否か)が次々と襲ってくる。本命かもしれぬ最後の1校まで我慢できず、入試戦線から脱落するケースも少なくない。そんなことにならぬよう、つまり本命受験までに少しでも安心材料を得られるよう、先輩の事例から併願戦略のヒントをお伝えしたい。そして、複数の大学を合格したらどの大学を選んだのかも参考にしてほしい。受験生たちの役に立てば幸いである。
焦り、怒り、ため息
「備えあれば憂いなし」とはよく言ったもので、普段の勉強もお金の備えも、そして併願への考えと情報収集も、備えておくことで安心して大学受験に臨めるもの。ところが冬から春にかけた受験期になると、必ずと言っていいほど焦りと怒りの声を、リアルの場でもSNS上でも見聞きする。
現在、大学に進学するルートは、大まかに学校推薦型選抜(公募制、指定校)、総合型選抜、スポーツ推薦、大学附属・係属校からの内部進学、そし
て一般選抜になる。進学割合は、一般選抜とその他のルートでほぼ半々だ。
一般選抜と学校推薦型選抜のうち共通テストを課すケースを除き、受験する学校数は基本的には1校で済む。言い換えると大学進学者の約半数は、複数校の受験(併願)を強いられることになる。国公立大学のみ、国公立大学と私立大学、私立大学のみのパターンがメインになるわけだが、短期大学や専門学校との〝両備え〟のケースも少なくない。
何校受験すればいいのか。難易度をどう振り分けて受験すればいいのか。共テ利用(併用)を使うのか使わないのか。受験する方式の受験教科・科目数は大丈夫か。地元で受験できるのか否か。英語外部試験は使えるのかどうか。受験料はいくらか。交通費はいくらか。合格した場合の入学料納入は
いくらで、何校分用意すればいいのか。
右の細かな説明は省くものの、挙げればキリがない。それほどまでに併願は奥が深い。そして、実際に対峙すると厄介なものだと感じるはずだ。我
が子の大学受験で「アリ地獄にはまった」と表現するある母親が言う。
「子供の第1志望は地方国立大学でした。共通テストの得点はボーダー以下。慌ててスベリ止めを探すハメに。ところが、探し始めると焦っているからか、どこがスベリ止めになるのか分からなくなるんです。いままでスベリ止めだと思っていたような大学でも『落ちたらどうしよう』と恐怖に襲われる。子供が怖がるのではなく、私ら親が怖がるんです。気が付くと、子供が望んでいない学部をピックアップしたりしていました。
学校や塾に相談して冷静さを取り戻しました。我に返ると、国公立なら2次の配点が高いところ、私立なら得意科目の配点が高い入試方式を利用するなど、いろんな選択肢があることを知ることができました。なのに、大学のランク、難易度だけで選ぼうとしていたんですね。
早い段階で情報を集めていれば、慌てることも焦ることもないと痛感しました。次の受験生の親御さんへアドバイスしたいなとも思いました」
高学力層は、難易度を下げれば合格可能な大学はいくらでもある。低学力層は、そもそも受験する大学を選べない。だから併願にそれほど悩みはしない。ボリュームゾーンの成績中位層は、できれば上を狙いたい欲と、万が一の時でも下は一定ラインに留めたいという欲の〝両欲〟と戦うことになる。だから焦りもし、怒ったりもするのだ。
併願受験は、もちろん強制ではないが、受験生からしてみればお守りそのもの。本命の前に合格を掴めれば安心して本命に臨める。ぜひ先輩らの併願
例を参考にしてほしい。本稿で国公立大学進学者の併願受験先を、次稿で私立大学進学者の併願受験先を考察していく。…続きは本誌で